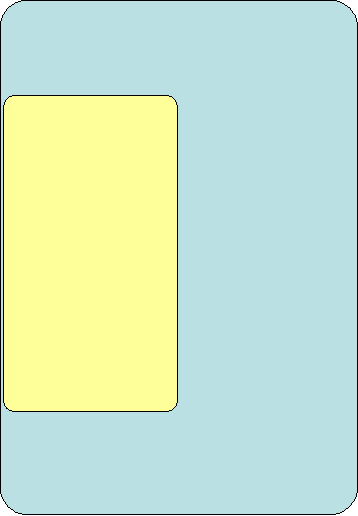
なゆた望遠鏡を用いた
次期小惑星探査候補小惑星、近地球型小惑星、及び、ベスタ族小惑星の可視分光観測計画
長谷川直1)・安部正真1)・黒田大介1,2)・森淳3)・時政典孝3)・尾崎忍夫3)
1)宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部、2)総合研究大学院大学、3)兵庫県立西はりま天文台公園
・小惑星を分光すると何がわかるか?
+大まかな表層の鉱物組成の同定が可能に
+隕石との比較が可能に
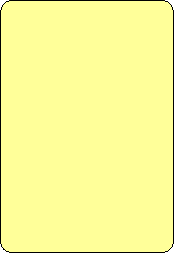

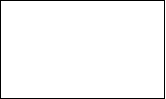
・小惑星の色と存在分布について
−Cタイプ小惑星:小惑星帯(2.2-3.3AU)の外側に多く存在
−Sタイプ小惑星:小惑星帯(2.2-3.3AU)の内側に多く存在
−Xタイプ小惑星:小惑星帯(2.2-3.3AU)に平均的に存在
−Dタイプ小惑星:木星トロヤ群(5.2AU)では支配的に存在
−Vタイプ小惑星:量は僅かで、ベスタ(2.3AU)付近に集中して存在
・小惑星の色と隕石との対応
−Cタイプ小惑星:炭素質コンドライト(始源的な未分化隕石)
−Sタイプ小惑星:普通コンドライト(落下数が多い未分化隕石)
:石鉄隕石(金属と岩石が混在している分化隕石)
−Xタイプ小惑星:鉄隕石(金属質の分化隕石)
:Eコンドライト(金属成分が多い普通コンドライト)
:変成したタギシュレイク隕石
−Dタイプ小惑星:タギシュレイク隕石(最も始源的な隕石)
−Vタイプ小惑星:HED隕石(玄武岩質の分化隕石)
・ベスタ族小惑星の分光探査の意義
+ベスタは小惑星帯の中で確認されている
唯一の地球型天体
+ベスタには族(軌道要素の似た天体の集
まり)があり、その起源はベスタ自身か
らでた破片と考えられている
+ベスタの周りにどれくらいベスタ起源の
小惑星があるか知りたい
−族を形成した時の衝突現象の規模の推
定
−近地球型小惑星やHED隕石への供給
元としての規模の推定
・近地球型小惑星の分光探査の意義
→近地球型小惑星の分布・起源の解明
・次期小惑星探査候補天体の分光探査
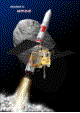

+はやぶさ探査機は小惑星イトカワを詳細
探査を行い、現在サンプルリターンを目
指して奮戦中
+はやぶさの次の小惑星探査を考えている
+探査計画としてはやぶさ計画の時と同様
に近地球型小惑星の探査を考えている
+但し、小惑星イトカワはSタイプ小惑星
であった為に、次回は異なるスペクトル
タイプの小惑星を考えている
+できれば、より始源的なCタイプ小惑星
の天体を探査したい
+しかしながら、現在の所、探査計画に適
当なCタイプ小惑星はみつかっていない
+そこで、なゆた望遠鏡にて、次期小惑星
探査候補天体探しを行う

Copyright. A, Ikeshita / MEF / JAXA, ISAS
・可視光分光による分別
+小惑星の分類は以下の2つで判別
1)コンティニュームの傾き
2)1μm付近の輝石・橄欖石起源のブロー ドな吸収の深さや幅
→つまり、0.5〜1.0μmにかけてのス
ペクトルができれば取得できれば、小惑星
のスペクトルタイプの判別が可能になる
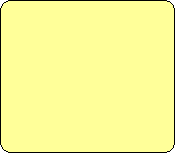
・小惑星可視分光用の概要
+なぜ、なゆた望遠鏡でなのか?
−シーイングの良さ
−観測を満たす精度の高いトラッキング(0.5秒角@10分間)
−現在ある可視分光器の一部パーツを取り替えるだけで実現可能
(フィルターホイールへの追加)
+小惑星分光用付加パーツの概要
−低分散グレーティング(150g/mm, Blaze800nm)
−幅広スリット(8秒角)
+対象となる小惑星の等級
−V等級で16等より明るい天体を対象にしている
+現状
−今週、評価の為のテスト観測を行った
−結果は現在解析中である

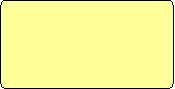
・小惑星分光の特異な点
+0.5〜1.0ミクロン(広波長範囲)で の%レベルの傾き測定
→現状ある既存の天文台の通常の分光器では この様な観測は難しい
→→小惑星のスペクトルを取得できるよう分 光器を新たに用意する必要がある