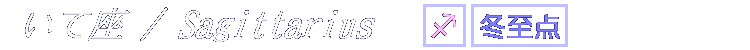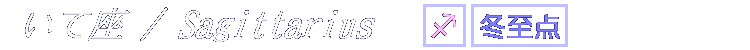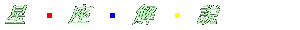
DUMMY
黄道第9星座,占星術では馬人(ばじん)宮.
設定者はプトレマイオス.
この星座の方向には天の川の中心があり,星雲・星団がたくさんあります.干潟星雲や三裂星雲は双眼鏡などでもよく見えます,また,現在,冬至点があります.
いて座の骨格を成している6個の星は北斗七星に似たひしゃく形で,中国では南斗六星,二十八宿では斗宿と呼ばれていました.また,英名ではミルクディパー(乳さじ)と言い,確かにそんな形にも想像できます.でも,大きさは北斗七星の半分程度しかありません.
天の川の中心,つまり,太陽系が入っている銀河系の中心はいて座の端にあります.いて座に向って見ると南斗六星の右下,いて座・さそり座・へびつかい座の境界あたりになります.さそりの尻尾の針先の左上というところです.この辺りが銀河系の中心だろうということは,まず1918年頃にシャプレーによって提唱されました.シャプレーは球状星団の距離を初めて求め,分布状態を明らかにしましたが,その分布の中心はいて座の方向にありました.1931年,ジャンスキーが銀河からやってくる電波をとらえたところ,それはいて座が高く上がっているときに最も強く現れており,いて座方向が特別なものであることが益々明らかになりました.しかし,この中心は望遠鏡では見えませんでした.途中の星間塵にはばまれていたからです.この段階では銀河系の中心が実体のあるものという認識は明確ではなかったようですが,1960年代になって赤外線や電波観測により直接銀河系中心からの放射が捉えられるようになり,銀河系中心にある核の存在が示されて,銀河系中心は核を中心とした天体の集合体であると考えられるようになりました.中心核の正体については研究中ですが,周辺にある諸天体が猛烈な勢いで運動していることからブラックホールのような小さいながらも大質量という天体が想定されています.
いて座の神話
いて座はケンタウロスとされていて,半人半馬の怪物です.下半身が馬で,そこから人間の胴体が延びています.人間の体のうち首と頭は馬でした.ケンタウロスは酒好きで粗暴な悪ものどもでした.いて座の射手もケンタウロスでしたが,これはケンタウロス族のリーダーのケイロンを表しています.
ケイロンは他のケンタウロスとはとても違っていました.実際,ケイロンは偶然のできごとからケンタウロスになったのでした.それは,父クロノス(タイタン族の年寄りのリーダー)が海のニンフのピリュラを誘惑して,彼が生まれたのでした.二人がクロノスの妻レアに驚いた時,やましい夫は妻の激怒から逃れるため自ら馬に変身しました.クロノスが変身したため,ピリュラとの間のその子は半馬になりました.これがケンタウロスのケイロンでした.
他のケンタウロスと違ってケイロンは賢く,学問に秀でていました.彼は文化の術,戦いの術では素晴らしい教師でした.ケイロンの洞窟は若いギリシャの英雄たちの教場となりました.イヤソン(金毛の羊をめぐる冒険の中心人物)とアキレス(トロイア戦争の英雄)の二人を立派にしたのはケイロンでしたし,へびつかい座として天に見えているアスクレピオスの先生はケイロンでした.
ケイロンの死は偉大な英雄ヘルクレスがケンタウロスのフォルスを尋ねたときに急に襲いました.フォルスはその英雄に酒樽から汲んだ一杯の酒をふるまいましたが,これがケンタウロス族の間で騒動を招くことになりました.ケンタウロスたちはヘルクレスにかかって行きました.ヘルクレスは彼らを巨大な弓で矢を放って後方に追いやりました.すると,ヘルクレスの放った一本の矢が偶然,何とか平和裏にことを納めようとしていたケイロンのひざを射ぬいてしまいました.ヘルクレスの矢にはうみへびの血が毒として塗ってありました.その矢の傷がもとでケイロンは死に,星座として祭られました.
|
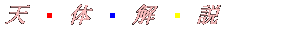
|
主な恒星 |
| 符号 |
名前 |
意味 |
等級 |
距離 |
| γ2 |
アルナッシュ |
矢の頭 |
3.0 |
125 |
|
スペクトル型:K0III,近接連星か
|
|
δ |
メディア |
弓の中央 |
2.7 |
85 |
|
スペクトル型:K2III
|
| ε |
カウス・
アウストラリス |
弓の南の部分 |
1.8 |
125 |
|
スペクトル型:B9IV.この星座で最も明るい
|
|
ζ |
アスケラ |
わきの下 |
2.6 |
140 |
| スペクトル型:A2III+A2V.周期21.14年の連星 |
|
λ |
カウス・
ボレアリス |
弓の北の部分 |
2.8 |
70 |
| スペクトル型:K2III. |
|
π |
アルバルダ |
|
2.9 |
250 |
| スペクトル型:F2II,三重星, |
|
σ |
ヌンキ |
海の指標 |
2.1 |
300 |
| スペクトル型:B2V,南斗六星に含まれる2等星,海の指標というのは「海の始まりの印」のこと,この星から東へ,山羊,海豚,水瓶,南魚,魚など,海(水)に関する星座が続くことに由来するようです. |
|
星雲・星団・その他 |
|
M8 (NGC6523):干潟星雲 |
|
散光星雲,7等,赤経18h20.7m,赤緯-16°11′.
|
|
M18 (NGC6613) |
|
散開星団,7.5等,赤経18h18.5m,赤緯-17°08′.
|
|
M20 (NGC6514):三裂星雲 |
|
散光星雲,9.0等,赤経18h2.3m,赤緯-23°2′.
|
|
M21 (NGC6531) |
| 散開星団,6.5等,赤経18h4.6m,赤緯-22°30′. |
|
M22 (NGC6656) |
| 球状星団,5.9等,赤経18h36.4m,赤緯-23°55′. |
|
M23 (NGC6494) |
| 散開星団,6.9等,赤経17h57m,赤緯-19°1′. |
|
M24 (NGC6603) |
| 散開星団,4.6等,赤経18h18.5m,赤緯-18°24′. |
|
M28 (NGC6626) |
| 球状星団,7.3等,赤経18h24.5m,赤緯-24°52′. |
|
M54 (NGC6715) |
| 球状星団,7.3等,赤経18h55.2m,赤緯-30°28′. |
|
M55 (NGC6809) |
| 球状星団,7.6等,赤経19h40.1m,赤緯-30°56′. |
|
M69 (NGC6637) |
| 球状星団,8.9等,赤経18h31.3m,赤緯-32°21′. |
|
M75 (NGC6864) |
| 球状星団,8.0等,赤経20h6.2m,赤緯-21°56′. |
|