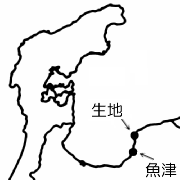春になると、「富山湾で蜃気楼が見えました」といった映像がニュースで流れることがあります。
蜃気楼は、海面付近に冷たい空気、その上に暖かい空気があるときに見える現象で、温度によって空気の屈折率が違うために、光が屈折して起こります。
蜃気楼といえば富山湾が有名なのですが、それは富山湾をはさんで能登半島が見えるようになるから…だと私は長い間、思い込んでいました。
さらに他にも、蜃気楼についてはいろいろと誤解していたので、ちょっとまとめてあげてみると、
1.富山湾でしか見えない?
2.水平線の向こうの能登半島が見える?
確かに蜃気楼の中にはふだんは水平線の向こうで見えないものが見えることもあるようなのですが、ふつう蜃気楼といえば上に書いたようにふだん見えている景色が変形して見える現象なのです。 3.誰もが注目する? 富山県魚津市では、春の天気のいい日には蜃気楼見物の人でごったがえすのですが…。 上の蜃気楼の写真を撮影した日、ゴールデンウィーク中の天気のいい日だったということもあって、琵琶湖畔には家族連れなど多くの人が集まり、釣りをしたりバーベキューをしたりしていました。 しかし、おそらく蜃気楼が見えていることに気づいていたのは、私を含め3人(あとの2人も蜃気楼を撮影するために来ていた人)だけでした。 というのも、蜃気楼で変形するの10kmくらい先の景色なので、双眼鏡があればよく見えるのですが、肉眼ではあまりわかりません。 この写真で左右が約3度しかありませんので、35mm版のカメラで700mmくらいの望遠レンズの画角に相当します。 蜃気楼はどんなふうに見える?
では、上の写真は蜃気楼が見えていないのかというとそうではなくて、ビルや観覧車の支柱の部分が上下に縮んでいて、そこから下の湖岸付近が上下に大きく伸びています。 非常にせまい範囲が上下に大きく伸びて見えているので、まるで湖岸に板塀が立っているような感じに写っています。 蜃気楼を見るには? 琵琶湖でも富山湾でも、蜃気楼は4〜5月頃の天気のいい、気温がぐんぐん上がっていくような日に発生しやすいのです。 2003年、琵琶湖のなぎさ公園おまつり広場では、2月に1回、3月に2回、4月に6回、5月にも6回(5月1〜5日は5日連続!)、6月に2回蜃気楼が確認されています。 富山まではちょっと…という方も、琵琶湖くらいまでならレジャーを兼ねて行ってみてはいかがでしょうか。 そのときには双眼鏡をお忘れなく。 写真を撮ろうという方は、望遠レンズを使うか、望遠鏡にカメラを取り付けるといいでしょう。 望遠レンズがない方は、デジタルカメラに双眼鏡を覗かせて撮影してみましょう。 うまくいけば写るかもしれません。
大阪市立科学館 友の会 『月刊うちゅう』 2004年4月号より一部加筆・修正 |