 �}�P�D�t�B�����P�[�X�ɐ��Ɠ����܂�����B |
 �}�Q. ��������Y�_�K�X�ň��͂��傫���Ȃ�A�ӂ����O�ꂽ�u�ԁB�t�B�����P�[�X�������Ŕ�яオ���Ă���B |
���s���Ȋw�ٌ�����14,159-162(2004)
�T�C�G���X�V���[�u���P�b�g�̂Ђ݂v���{��
�֓��g�F
���s���Ȋw��
�T�v
���P�b�g���������錴����̊����A��p����p�̖@����m�邱�Ƃ�ڕW�Ƃ��āA2003�N�U�`�W���ɃT�C�G���X�V���[�u���P�b�g�̂Ђ݂v�����{�����B
�P�D�͂��߂�
���P�b�g�͎q�ǂ������l�ɂ܂Ŕ��ɐl�C������B�����āA���P�b�g�̌���������������������������B�����ŁA���P�b�g���������錴����̊����A��p����p�̖@����m�邱�Ƃ�����̃T�C�G���X�V���[�̖ڕW�Ƃ��A�T�C�G���X�V���[�u���P�b�g�̂Ђ݂v���l�āE���{�����B�{�e�ł́A2�͂ʼn������e���A3�͂Ŋe���������̃m�E�n�E���A4�͂ŃT�C�G���X�V���[�����{�������z�Ȃǂ��q�ׂ�B
�Q�D�������e
�i�P�j����
�R�ăK�X���˂̔���p�Ń��P�b�g���������邱�Ƃ�m��B
�i�P�|�P�j�t�B�����P�[�X���P�b�g
�t�B�����P�[�X���P�b�g���X�e�����X�����ʊ�ɏՓ˂��鉹�ŋ�������B
 �}�P�D�t�B�����P�[�X�ɐ��Ɠ����܂�����B |
 �}�Q. ��������Y�_�K�X�ň��͂��傫���Ȃ�A�ӂ����O�ꂽ�u�ԁB�t�B�����P�[�X�������Ŕ�яオ���Ă���B |
�i�P�|�Q�j��b�T�O����
���݂�ɂ����t�B�����P�[�X���P�b�g��J�G���̂���������g���A�t�B�����P�[�X���P�b�g�͐��˂��邱�Ƃʼn������邱�Ƃ�m��B���P�b�g�͔R�ăK�X�̕��˂ʼn������邱�Ƃ��������B
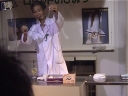 �}�R�D�t�B�����P�[�X���P�b�g�𒈒݂�ɂ����ꍇ�B |
 �}�S�D�ӂ����O�ꂽ�u�� |
 �}�T�D������̂�������ōl�@ |
�i�Q�j����p�̗Ꭶ
�K�X�̕��o�ɂ�锽��p��Ꭶ����B
�i�Q�|�P�j���P�b�g���D
�t�B�����P�[�X���P�b�g�̍l�@���烍�P�b�g���D���Ȃ���Ԃ����l����B
 �}�U���P�b�g���D |
�i�Q�|�Q�j�u�����[���1
���P�b�g���D����A����Ɍ��ۂ�傫�����A������[��������B
 �}�V�D�u�����[�Q����Œ肵�A�Ђ��̏�ɂ�����悤�ɂ������� |
 �}�W�D�u�����[�Q�䂩�琁���o���C�̔���p�ŁA���[�����l���悹����Ԃ���������B |
�i�R�j���P�b�g�R���Ɣ���
�@�����ɂ��A�K�X�����o���邱�Ƃ�m��B
�i�R�|�P�j�t�̔R��
�@���P�b�g�̉t�̔R���Ɠ��������A���f��_�f�����K�X�̔���2�Ŕ����������邱�Ƃ��m�F����B�傫�Ȕ����������ʉ��Ƃ��āA�����ŃK�X�����˂��邱�Ƃ�������B
 �}�X�D���f�E�_�f�����K�X���`���[�u�ɓ���A�d�q���C�^�[�̉ΉԂŒ�����B |
 �}�P�O�D�傫�Ȕ������Ɠ����ɔ����Ń��[�g�ɓ��ꂽ���Ђ������オ��A���ӂԂ����ł���u�ԁB |
�i�S�j���P�b�g����
�@�����ɂ�胍�P�b�g����Ԃ�����m��B
�i�S�|�P�j�}�b�`�_���P�b�g3�@
�@�ő̔R���̐����ƁA�ő̔R���̗Ꭶ�B�����ȃ}�b�`�_���\�z�ȏ�ɍ����Ŕ�т�����l�ŋ������������A������[��������B
 �}�P�P�D�}�b�`�_�̐���A���~���ŕ�݁A�j�ŔR�ăK�X�̕��o�����J���A���ˑ�ɃZ�b�g����B |
 �}�P�Q�D�R�ăK�X���o���Ȃ���}�b�`�_����яオ��u�� |
 �}�P�R�D���o�����R�ăK�X���}�b�`�_�̔�Ղ�`���B |
�i�S�|�Q�j�ŏ��̃��P�b�g3
�@�ő̃��P�b�g�̎��H��Ƃ��āA�������̉Ζ��A�ŏ��̗L�l���P�b�g�̈�b��͌^��C���X�g�������Đ�������B
 �}�P�S�D�͌^�Œ����̈�b���Љ� |
�i�S�|�R�j�A���~�ʃ��P�b�g4
�@�������o����̂̂قƂ�Ǔ����Ȃ��B���w�҂̊��҂𗠐�A���̎����̌��ʂ����߂邽�߁A�����ē����̏����Ȍ��ۂ�������B
�@���ˑ�̒P�����ɔ����đz���ȏ�ɑ傫�Ȍ��ۂŁA���w�҂͋����B���O�̏����Ȍ��ۂ����w�҂̔�����傫������B�X�e�����X�̐��ʊ�ɏՓ˂��鉹�������ʂ����߂�B
�@�������A�V�����_�[���g���Ă���̂ŁA����ɍH�v���K�v�B���҂́A�u���������ɓ�����A�����璵�˕Ԃ�A�ʂ������A�܂����˕Ԃ�A�E�E�E�A�����̍ė��p�v�Ɛ��������B
 �}�P�T�D�A���~�ʂɉR�K�X����ꒅ�B�������邪�قƂ�ǔ�Ȃ��B |
 �}�P�U�D�R�s�[�p���ō�����V�����_�[�ɃA���~�ʂ����A�ēx�����B |
 �}�P�V�D�A���~�ʂ���яオ��u�ԁB�A���~�ʂ͏㕔�̃X�e�����X�̐��ʊ�ɂԂ���A�傫�ȉ����o���B |
�i�S�|�S�j�E�C�X�L�[���P�b�g5
�@�g�߂Ȃ��̂Ƃ��āA�E�B�X�L�[��R���Ƃ���B�E�B�X�L�[���������錴����������A�u�E�B�X�L�[����������H�v�Ƃ������M���^�̃X�g���X�����w�҂ɗ^���Ă����B���̌�A���w�҂̓�������B�y�b�g�{�g�������R�Ăɂ����邱�ƁA�������y�b�g�{�g�����琁���o�鉹�A�y�b�g�{�g���̔�ԑ����A�ȂǑz�����錻�ۂŁA���Q�̐���������B
 �}�P�W�D�y�b�g�{�g���ɃE�C�X�L�[������B |
 �}�P�X�D�M���ʼn��߁A�A���R�[��������������B |
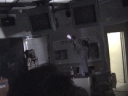 �}�Q�O�D�y�b�g���ŃA���R�[�������j�����u�ԁB���̐ՁA�y�b�g�{�g���̓^�R���ɉ����Č��w�҂̓�����ԁB |
�i�T�j�܂Ƃ�
�@���P�b�g����Ԍ�������ʉ��������̂Ƃ��āA��p����p�̖@����[�������A�j���[�g�����Љ��B
 |
�R�D�m�E�n�E
�P�D �t�B�����P�[�X���P�b�g
�@ �t�B�����P�[�X�ɓ���鐅�̗ʂ́A�t�B�����P�[�X�̔����ʂ��悢�Ǝv����B���ʂ������Ă����Ȃ��Ă��A�����悭��Ȃ��B
�A
���ʉ����o�����߁A�X�e�����X�̐��ʊ�Ƀt�B�����P�[�X���Փ˂������B
�Q�D ���f�E�_�f�����K�X�̔���
�@ ���̓d�C�����ɂ�萅�f�K�X�Ǝ_�f�K�X���������B���������g���ƁA���炭����Ɠd�ɂɉ������t�����A�K�X�̔����ʂ���������B�����̎g�p��E�߂�B
�A �_�f�K�X�Ɛ��f�K�X��~����`���[�u�������ɕۂƁA�����Ȃ����Ƃ�����B���f�K�X�Ǝ_�f�K�X����������̂�������Ȃ��B���̓d�C�����ō����K�X�������A�{���x���璼�ړ�������悢��������Ȃ��B
�R�D �}�b�`�_���P�b�g
�@ �}�b�`�_�̐���A���~���ŕ�ނƂ��A�R�ăK�X�Ŕj�Ȃ��悤�ɁA���łɊ����B
�A ���o���͐��ӏ�����Ƃ悢�B��ӏ��̏ꍇ�A���̕��o������R�ăK�X�����o�����A�A���~�����j��A��Ȃ��ꍇ�������B
�S�D �A���~�ʃ��P�b�g
�@ �A���~�ʂ̑����ɒ��Ηp�̌��i���a5mm���炢�j��������B
�A �V�����_�[�̓R�s�[�p���ȂǏ_�炩�������悢�B�܂��A�A���~�ʂƂ̌��Ԃ��R�s�[�p��1�������炢��������Ƃ悢�B
�T�D �E�B�X�L�[���P�b�g
�@ �y�b�g�{�g���͑ϔM�ψ��p�̂��̂�p����B�ϔM�łȂ��ꍇ�͔M���łԂ��B
�A �y�b�g�{�g��(1.5���b�g��)�ɃE�B�X�L�[5cc�����A�M���̓������d�C�|�b�g��10�b�Z���ĉ��߁A�O��30�b��₷�ƁA��������̂ɂ悢�����̂悤�ł���B���߂āA�����ɒ����悤�Ƃ��Ă������Ȃ����Ƃ������B
�B �y�b�g�{�g���̂ӂ��ɁA���o�������Ηp�̌����J����B���a5mm�ȏ�B�����������ƁA�j��A�ӂ�����ԂȂNJ댯�B
�C
���o����K�X�͍����Ŋ댯�B
�D
�^�R���ɉ����Ĕ�����߂ɁA�X�g���[���y�b�g�{�g���ɃZ���e�[�v�œ\��t���A����Ƀ^�R����ʂ��B
�S�D�܂Ƃ�
���͂�������̘A���ōD�]�ł������B�����Ɖ�����H�v���邱�ƂŁA���_����Ƃ����v�l�𑣂����Ƃ��\�ł���B�y�������Ԃ��߂����Ȃ���A���R�ƍ�p����p�̊T�O��^���邱�Ƃ͂�����x�ł����Ǝv���B�������A�����̈�b�ȂǗ��j�I�Șb��͌��w�҂����̌��ۂ����҂��Ă��邽�߂ł��낤�A�����������Ȃ����Ƃ������������B
�����̌��w�҂͉Ȋw�I�v�l�Ȃ��ł����ۂ����邾���Ŗ�������B�v�l�������X�����炠��B�������A�Ȋw�I�v�l�Ŗ������Ă����������Ƃ���ɐS�����������̂ł���B
�P�D���P�b�g�����ł��鎞�Ԃ̂قƂ�ǂ������^���ł���B�����^���Ɖ����^���̈Ⴂ���Љ��ׂ��ł���B
�Q�D���P�b�g�̐�[�Z�p���Љ��ׂ��ł���B
�ᔻ�����������āA���ۂɌ��y���邱�Ƃ����݂��B20���Ԃ̉����Ƃ��������邽�߁A����T�O�𑝂₵�����A���e�������Ȃ�͔̂������Ȃ������B�����A�����ɂ��Ă����y���邱�Ƃ��ł����痝�z��������Ȃ��B�m���𗅗邾���Ȃ����T�O�𑝂₷���Ƃ͉\�ł���B�������A�Ȋw�I�v�l���y���ނ��߂ɂ́A��p����p�̖@����ڕW�Ƃ���̂��K�ł������Ǝv���B
�Ƃ���ŁA�\1�Ɏ������悤�ɁA���s���邱�Ƃ����X�������B�����҂ɂ���ẮA�����̈ꕔ����������ꍇ���������B
�\�P�D���s���e�ƌ���
|
�����Ȃ����Ƃ�����B�����s�� |
|
|
�}�b�`�_���P�b�g |
��܂��A���~�����R�ăK�X�ɂ�鍂���Ŕj�A��Ȃ��B |
|
�E�B�X�L�[���P�b�g |
�����Ȃ����Ƃ�A�R�Ă����͂ɂ������Ƃ�����B�M���ʼn��߂�����́A�A���R�[�������������āA�_�f�s���Ǝv����B |
�ӎ�
�����̊F�l�ɂ́A�L�Ӌ`�ȏ����𑽂������������B�܂��A�T�C�G���X�V���[������ɎQ�������������݂Ȃ��܂�����M�d�Ȉӌ������B�����Ɏӈӂ�\���܂��B�܂��A�i�L�j�ʔ��p�H�[�̏���r�ɂ͍ŏ��̗L�l���P�b�g�͌^�A(�L)�A�N�Z�X�̑��쎡�N���ɂ̓u�����[��Ԃ̐���ɋ��͂����������B�����Ɏӈӂ�\���܂��B
�r��
[1] ���m�E�E�O�d�����T�[�N���F�������������킭�킭�����Q,���{�]�_��
[2] ���쏹�O�F���s���Ȋw�ٌ�����, No8,77
[3]�@http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/aeroact.htm
[4] ���쏹�O���F���s���Ȋw�ٌ�����,No3,75
[5] ���쏹�O�F���s���Ȋw�ٌ�����,No4,103
[6] ��11��T�C�G���X�V���[������