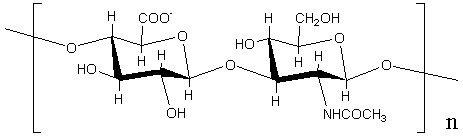暮らしのなかの化学をたのしもう
岳川ゆきこのホームページへようこそ
■ヒアルロン酸で美しくなれる ?!■
最近CMや化粧品などで、「ヒアルロン酸」をよく見かけます。「ヒアルロン酸配合の化粧品、お肌がぷるぷるつやつやに…」。もしこれがほんとうだったなら、なんてすばらしい物質なのでしょう。
■ヒアルロン酸はこんな化学物質
ヒアルロン酸は、1934年にコロンビア大学のメイヤー(Karl Meyer)教授らが牛の眼のガラス体から分離したのが初めてで、ギリシア語のHyaloid(ガラス体)、多糖体の構造単位(Uronic asid:ウロン酸)から、Hyaluronic asid(ヒアルロン酸)と命名したのも彼でした。この分子構造は、それから約20年後に彼らの研究室で決定され、生体内ではイオンとして存在することから、1986年にはHyaluronan(ヒアルロナン)が正式名称となりました。日本では、過去の名前「ヒアルロン酸」の方がよく使われているというわけです。
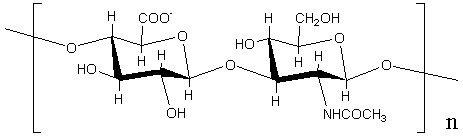
ヒアルロン酸は、D−グルクロン酸(向かって左の六角形の部分)、D−N−アセチルグルコサミン(向かって右の六角形の部分)、この2つの"糖"が交互に鎖のように結合した高分子多糖類の一種です。このヒアルロン酸の鎖は、途中で枝分かれすることなくまっすぐにつながって、その分子量はおよそ400万(この2つの糖が約1万ペア結合している計算、n=約10000ということ)になります。
■ヒアルロン酸と人間のからだ
何といってもヒアルロン酸の特徴は、高い粘性と保湿性で、ヒアルロン酸1gで6リットル、つまり6000倍もの重さの水を吸収、保有することができます。おなじように、水を吸収できる物質として紙おむつや生理用品などに利用されているいわゆる「高分子吸収剤」があります。こちらは、ポリアクリル酸ナトリウムが成分で、自重の約500倍程度の水を吸収することができます。
ヒアルロン酸は生まれつき私たち人間の体にあって、最も多い部分がさい帯(へそのお)で約4mg/ml。さい帯は産まれてすぐになくなりますから、ふつう体内で最も多いのは皮膚(約7g)で全体の約50%を占めます。このほか、眼のガラス体(形の維持)、関節(動きの潤滑作用)、細胞間(細胞のクッション、水分の保持)など、それぞれの場所で役割を果たしています。
体内のヒアルロン酸は、代謝(作られたり分解されたり)を繰り返しています。正常な軟骨では半減期(量が半分にまで減る時間)は約2〜3週間、代謝が活発な皮膚の角質細胞では半減期は1日以下。全体的に見ると体内の約3分の1のヒアルロン酸が、1日で新しく生まれ変わっているそうです。ちなみに新しいヒアルロン酸は、ヒアルロン酸合成酵素によって作られています。
ところが歳を重ねるごとに、体内のヒアルロン酸の量は減少していきます。20才時の所持率を100%とすると、30歳で65%、40歳で45%、60歳で25%…。これはなんともショッキングなデータです。代謝の分解スピードに、合成スピードが追いつかない、ということでしょうか。また、ヒアルロン酸の量の減少だけが原因ではありませんが、体内の水分量も、幼児が80%、成人70%、高齢者50%、と同じく年を重ねるにつれて少なくなるというデータもあります。
■「美」と「医」とヒアルロン酸
「美」(美容分野)では、保湿目的の化粧品への添加、美容整形ではシワに注入して肌のハリを復活させる方法などでヒアルロン酸が利用されています。「医」(医療)分野では、1950年代後半に眼科手術でのガラス体の補充が行われたのが最初で、このときに使われたヒアルロン酸はヒトのさい帯から、その後、鶏のトサカ(さい帯以上の7.5mg/mlを含む)から単離、精製されたものが利用されました。現在でも、眼科手術と並んで関節の機能改善治療(関節に直接注射して動きをスムーズにする)によく使われており、ヒアルロン酸も微生物(溶血性連鎖球菌)による発酵で合成されるものもあります。
実は私、2ヶ月ほど前からヒアルロン酸配合の化粧水を使い始めました。自分のからだで実験、というわけです。ねっとりしていて、肌につけるとしっとり(というかべっとり)して、これまでの化粧水とは感触は違います。私のお肌がぷるぷるになったらみなさんにもオススメしようと思っていたのですが、今のところ効果はよくわかりません…。でも今回のこばなしでは、ヒアルロン酸は肌の表面に塗るだけではなかなか「美」「若」を保つのは難しそう、ということでしたね。
次回は、こちらも今話題の「コエンザイムQ10」についてご紹介しましょう。
■参考文献
「月刊 化学」(化学同人 2004年9月号28頁「ヒアルロン酸の驚異に迫る!」)
「ヒアルロン酸:その構造と物性」V.C.Hascall&T.C.Lairent(1997)
(2005.3.25.更新:岳川有紀子)
大阪市立科学館 > 学芸員たち > 岳川ゆきこのホームページ