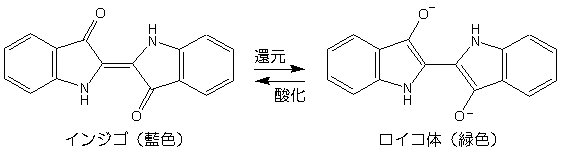暮らしのなかの化学をたのしもう
岳川ゆきこのホームページへようこそ
■青は藍より出でて藍より青し■
これは荀子(じゅんし:紀元前3世紀頃の中国の思想家)が残した言葉の一部です。もとの藍の色よりも濃い色になるという意味で、弟子がその師をしのいで優れたときに使われます。「学は以って己むべからず、青はこれを藍より取れども藍より青く、氷は水これをなして水よりも寒し」(荀子勘学篇)。こんな言葉からも、藍が古くから使われていた染料だということが分かりますね。
さて私、夏休みを利用して四国に行ってきました。徳島で藍染体験をしてきたのでご紹介したいと思います。といっても、布を浸す直前まで準備されていたので、体験してきたのは藍染めのほんの一部なのですが…。
藍染めをしてみよう
まず木綿の布をもらって、染め上がった際に模様ができるように布の一部を縛ります。そして割烹着を着て手袋をしてから染色です。布を紫色の液(藍液)がたっぷり入った大きなかめの中に浸します。布を藍液に浸すこと約20秒、布を上げると白かった布が緑色になっています。緑色とは予想外の色ですが、布を広げる作業をしていると次第に緑色が青く、藍色に変化してきます。この色の変化については後ほどご紹介しますが、藍液に浸しては広げるという作業を3回繰り返し(繰り返す回数が多ければそれだけ濃く染色できる)、激しく水洗いをして、アイロンで乾燥させると完成です。

藍が染料になるまで
藍はご存知のように植物で、日本では主に蓼藍(たであい)という種類の葉が染料の主原料となります。藍の葉を収穫し、発酵させ、染料の原料となる「すくも」を作るまで1550年頃からはじまる伝統的な方法では4ヶ月以上が費やされる非常に厳しい仕事です。そしてこのすくもを練って水に溶かして藍液を作ります。しかしすくもに含まれる藍色の物質「インジゴ」は水に溶解しない性質を持っているので、このままでは染料にはなりません。そこで灰汁などのアルカリ性の物質とすくもと一緒に混ぜることによって、インジゴを化学反応(還元)させ、水に溶解するロイコインジゴ塩(ロイコ体)という物質に変わることを利用して、布を染めることができる藍の水溶液(藍液)をつくっています。
緑色→藍色の理由
さて、布が最初に染まった予想外の緑色は、実はロイコ体の色です。ロイコ体は空気(のなかの酸素)に触れると、化学反応(酸化)され、元のインジゴに戻ります。これが布が緑色から藍色に変化する理由です。
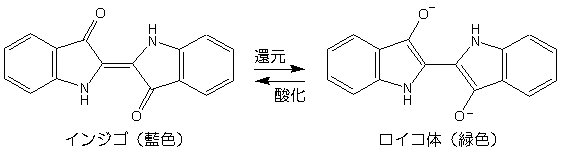
したがって藍染めをするときには、藍液に浸した後、布をしっかり広げて空気によく触れるようにしてあげることが大切です。このように、すくもに含まれるインジゴを還元し、藍液に含まれるロイコ体に変え、布でロイコ体を酸化して再びインジゴに戻す、という物質の化学反応による変化が、化学的なことはわからない時代からの染色の方法として利用されているのです。
展示場4階の20世紀の科学「染料」に藍(タデ藍)の押し葉・すくも・藍で染めた布、また1870年に藍の色を人工的に出すために発見された合成インジゴなどを展示しています。機会があれば、ぜひ展示で実物もご覧ください。

藍のちから
合成インジゴが発明された後、天然藍は急激に衰退します。天然藍は虫除けなどの効果があり、古くから農作業の作業着は藍で染めていたということです。藍は薬学博士 村上光太郎氏によると、以下のような効果があるということです。
・青藍を粉末とし服用すれば食道がんや胃がんによる嘔吐に効果がある。
・生葉汁を塗布するとやけど・口内炎・毒虫の刺し傷に効果がある。
・藍葉・藍実を煎じて服用すれば、解毒・解熱剤として効果がある。
おしらせ
このように、藍という染料ひとつとっても、化学的・歴史的に奥が深いですよね。10月からの化学実験講座では「染料の化学」をテーマに、染料の歴史や染色の化学を取り上げます。染料の化学に興味をお持ちの方の応募をお待ちしております。
※この実験教室の募集は終了しています。
(岳川有紀子:科学館学芸員)
(2004.11.26.更新)
大阪市立科学館 > 学芸員たち > 岳川ゆきこのホームページ