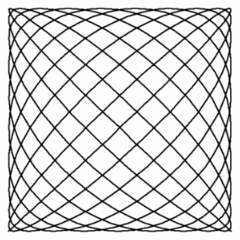科学教室「ふしぎな振り子」実施報告
長谷川 能三
大阪市立科学館
概要
|
1999年6月の楽しい科学実験「ふしぎなふりこを作ろう」では、左右にゆらしても前後に振れるようになるふしぎな振り子作りを行なった。
しかし楽しい科学実験では、じっくりと関連実験を行なったり解説したりすることができず、簡単な仕組みを書いたテキストを配布するにとどまった。
そこで、振り子に関する実験を含めた科学教室としてあらためて実施したので報告する。
|
|
1.ふしぎな振り子
このふしぎな振り子は、糸をY字型に結んだ振り子で、Y字型の糸の吊り位置を45度斜めにずらしたものである。
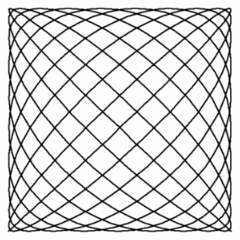 |
|---|
| 図1.リサージュ図形の例 |
|---|
そもそも糸をY字型にした振り子はブラックバーンの振り子と呼ばれ、左右に振らせた場合と前後に振らせた場合で、揺れに有効な糸の長さが違うため、揺れの周期が少し異なる。
このような振り子は、例えば左手前から振り子を振らし始めると、最初のうちは左手前と右奥の間で揺れているが、次第に左右の揺れとと前後の揺れの位相がずれてくるために左奥と右手前の間で揺れるようになり、もうしばらくするとまた左手前と右奥の間で揺れるようになり…、と揺れの方向が変化する。
左右と前後の振動周期が近いと振動方向の変化はゆっくりで、振動周期が大きく異なっていれば振動方向が短時間で変化するようになる。
このような振り子が描く軌跡は、一般にリサージュ図形という。
今回のふしぎな振り子は、このブラックバーンの振り子の2ヶ所の吊り下げ位置を、左右ではなく、右手前と左奥というように45度斜めにずらしたものである。
すると、左右に振らすことが、Y字型の面に対しては左手前と右奥の間で振らすことになる。
このため、しばらくしてY字型の面に対して左奥と右手前の間で揺れるようになるということが、振った人にとっては振り子が前後に揺れるようになると見えることになる。
ブラックバーンの振り子でリサージュ図形を描かせるのは演示実験や展示でよく見かけるが、この振り子では軌跡を追わなくても非常にふしぎな動きに見え、興味を持つきっかけとなる。
2.実施日時
| | 2000年4月5日(水) | 14時~15時30分 | 参加23名 |
| | 6日(木) | 14時~15時30分 | 参加19名 |
3.内容
教室では、振り子の周期はどのような場合にどのように変化するかといった実験・学習を行なった上で、Y字型に糸を結んだのブラックバーンの振り子の動きを調べた。
その後、板やアルミ棒などを使って各自ふしぎな振り子を製作し、持ち帰った。
- (1) 振り子とは
-
振り子は、糸の先におもりをつけるだけでもつくることができるが、その特徴は一定の周期の運動を繰り返すことにある。
この周期が一定であることは振り子時計などに使われている。
当日の参加者は小学生(参加対象は小学新4年生以上)が多く、古い振り子時計を見せたところ、このような時計を実際に知っているのは半分強といったところであった。
- (2) 振り子の周期
-
実験では、振り子の振幅・おもりの重さ・糸の長さを変化させた場合に周期が変化するかどうかを調べた。
振り子はサイエンスショーなどでも用いている鉄棒型のフレームにぶら下げ、振り子が10往復する時間を参加者2名がストップウォッチで計測した。
2名が計測することにより測定にはある程度誤差が含まれていることも参加者は自然と会得したようで、測定誤差もしくは測定誤差に埋もれる程度の差と、有意な差とを区別することができた。
この実験により、振幅やおもりの重さを変えても振り子の周期に有意な差は現われないが、糸の長さが違うと周期が異なることがわかる。
- (3) ブラックバーンの振り子
-
 |
|---|
| 写真1.教室のようす |
|---|
次に、糸をY字型に結んだブラックバーンの振り子の動きを観察した。
まず、ブラックバーンの振り子を、Y字型の面に対して左右のみや前後のみに動かして、どのような動きになるか観察した。
その結果、Y字型の面に対して左右に振った場合には、結び目より下だけが揺れ、結び目から下の糸の長さの振り子と同じ動きになることを確かめた。
また、Y字型の面に対して前後に振った場合にはY字型の糸全体が揺れるが、糸の取り付け位置の高さからおもりの高さまでに相当する長さの糸の振り子と同じ動きになる。
次に、このブラックバーンの振り子をY字型の面に対して左手前から振った。
こうすることによって、左右の動きと前後の動きが同時に起こることになる。
しかしこの動きをY字型の面の真正面や真横から観察すると、振り子の左右の揺れや前後の揺れは、振り子を左右だけもしくは前後だけに振った場合と同じであることを観察した。
最後に、左右と前後の両方に揺れているブラックバーンの振り子を、斜めから観察した。
すると正面や真横から見た場合には普通に揺れているように見える振り子が、大きく揺れたりほとんど揺れなくなったりまた大きく揺れるようになったりと、振幅が大きく変化して見えることがわかる。
- (4) ふしぎな振り子の製作
-
今回の科学教室では振り子の製作にある程度時間を割けることもあり、インテリアとしても利用できるような形態とした。
振り子の土台として、黒のカラーシートを貼り付けた板に、直径3mm・長さ50cmのアルミ棒を次ページのテキスト表紙の絵のように曲げてさし込んだ。
また、振り子のおもりには直径約18mmの鉄球を用いた。
この鉄球と振り子の糸をつなぐのには、最初一般の接着剤を使用しようとしたが乾くのに時間がかかるなど問題があったために、ホットボンドを使用した。
ホットボンドは、ピストル型で先端が熱くなる機器を用いて、熱で融かして使うものである。
融けたホットボンドを機器の先端から出し、冷えて固まるとくっつくというものである。
接着するものの素材によって、よくつくものとあまりつかないものがあり、今回も鉄球に対する接着力は弱かったが、能率よく接着できることと、持ち帰った後ではずれた場合にも、ひも側に残ったホットボンドに通常の接着剤を塗ることで接着できることから、ホットボンドを使用した。
また、アルミ棒に結びつけたひものゆるみ防止のためにもホットボンドを使用したが、結線バンドで固定する方が能率的だったかもしれない。
4.テキスト
当日配布したテキストは次ページの通りである。
5.考察
このふしぎな振り子は、その動きの不思議さによる興味と、原理が比較的単純なこと、糸でおもりをつるした振り子の周期が糸の長さで決まることから、振り子の学習に適した素材であると考えた。
当日も振り子の動きに関する実験に主眼を置き、通常の科学教室とは机の配置を変えて、全員が大きな振り子に向かって座れるように工夫した。
[参考文献]
長谷川 能三
『楽しい科学実験「ふしぎなふりこを作ろう」実施報告』 大阪市立科学館研究報告№10,133 (2000)
|
|